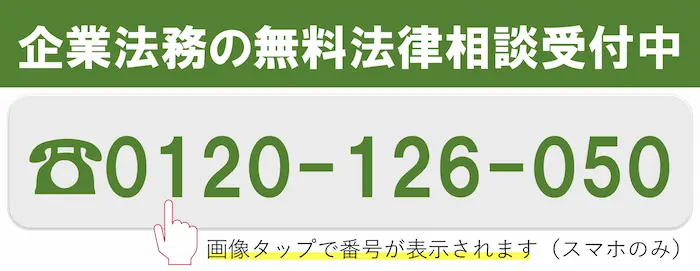会社と法人格について(会社法3条、104条等)
(法人格)
第三条 会社は、法人とする。
(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
株式会社は法人であるため(会社法3条)、法律上、代表取締役や株主とは別個の権利義務の主体として認められています。例えば、株式会社の借金は、株式会社のみが負うことになり、株主に返済義務はありません。
もっとも、株式会社は自然人とは異なるため、権利義務が制限される又は権利義務の独立した主体とは認められないか等の問題が生じることがあります。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
定款所定の目的による権利能力の制限
定款所定の目的外の取引も有効性が認められる
株式会社が行った取引が定款の目的外である場合に、その取引の有効性が問題になることがあります。この点について、改正前民法43条が法人の権利能力が定款で定められた目的により制限されることを規定していたため、判例は同条を類推適用して、会社も定款の目的により権利能力が制限されるとしています。
しかし、現実には定款に記載のない事項であっても、会社の目的を達成するために必要な行為は定款の目的の範囲内であり株式会社に権利能力があるとされています。そして、判例は、定款の記載自体から客観的・抽象的に必要であり得るべきかどうかを基準として、会社の目的を達成するために必要な行為であると判断しています(最高裁昭和27年2月15日判決)。したがって、実際は定款所定の目的に記載のない取引であっても、幅広く取引の有効性が認められると考えて良いでしょう。
株式会社が政治献金を行うことの当否
この点に関連して、株式会社が政治献金を行うことが定款所定の目的に含まれるかが問題となることがあります。
判例は、政治献金は定款所定の目的を達成するために必要・有益な行為であるとして、権利能力の範囲内に含まれると判断しています(最高裁昭和45年6月24日判決)。但し、政治献金の金額が合理的でない場合には、取締役の善管注意義務・忠実義務違反に基づく損害賠償責任等が生じることはあり得ます。
法人格否認の法理について
法人格否認の法理とは、株主と会社を同一視するべき場合において会社の法人格の独立性を否定し、会社・株主を同一視するものです。
例えば、会社代表者でない株主は、会社を代表する権限を持たないため勝手に会社の資産を売却することができません。しかし、判例は、法人格否認の法理を適用し、会社代表者でない株主がした会社資産の譲渡を有効と判断する場合があります(最高裁昭和47年3月9日判決)。
法人格の濫用
株式会社の法人格が法律の適用を回避するために濫用された場合、民法1条3項を根拠として法人格否認の法理が適用されることになります。
法人格が濫用されたと言えるためには、会社の背後にある支配株主が法人格を完全に支配していること(支配要件)と、債務負担の回避等の違法・不当の目的が存在すること(目的要件)が必要であると考えられています。
例えば、多額の負債を抱えた会社(旧会社)が新たに設立した会社(新会社)に事業譲渡をしたような場合において、このような事業譲渡が旧会社の債権者からの強制執行を免れるために行われたと判断されたような場合には、旧会社と新会社が同一の責任を負うと判断される可能性があります(大阪高裁平成12年7月28日判決、福岡地裁平成16年3月25日判決)。
法人格の形骸化
支配株主が株式会社の法人格を完全に支配していることに加えて、以下のような事情があるときには法人格が全くの形骸にすぎないとして法人格否認の法理が適用されることがあります。
- 会社と支配株主の財産や業務が混同している場合
- 株主総会・取締役会の不開催等の会社法等の手続きが順守されていない場合
株式会社の中には、株主が一人であったり、小規模な同族会社であったりすることが少なくありません。このような会社においては、個人・会社の権利関係が不明確である、又は会社法の手続きが一切行われていないことが横行しています。しかし、きちんと会社法の手続き等を行っておかないと法人格の形骸化が認められて、株主が思わぬ責任を負うリスクがあるので注意が必要です。
裁判例においては、株式会社の債権者が実質的なオーナーに対して売掛金の請求を行った事案において、株式会社は形骸化した会社であるとして法人格の否認の法理を適用し、実質的なオーナーに対する売掛金の請求を認めた事案等があります(東京地裁平成2年10月29日判決)。
偽装解散と解雇における法人格否認の法理の適用
法人格否認の法理は、解雇の場面においても問題となることがあります。例えば、労働組合員の排除やリストラ・人員整理等を目的として、現在の会社を解散することにより従業員を解雇し、新たに設立した会社で一部の従業員のみを再雇用して事業を再開するような場合に法人格否認の法理が適用できるかが問題となり得ます。
この点、裁判例においては、株式会社が偽装解散し、その後に新会社を設立して同じ事業活動を再開した場合には、労働者は新会社に対して雇用の継続を主張できると判断したものがあります(大阪高裁平成17年3月30日決定)。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします