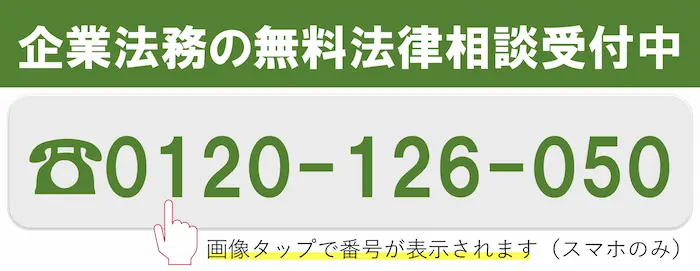この記事ではM&Aトラブルの紛争解決条項について、以下の点を解説します。
- M&A契約の「専属的合意管轄」が何を意味し、どう書けばよいか
- 仲裁合意(仲裁条項)を入れる場合に、どこまで決めておくべきか
- 準拠法条項と、紛争時に揉めやすい周辺条項(完全合意・権利不放棄・契約譲渡禁止)の注意点
- 複数契約・クロスボーダーで条項が“矛盾”しないためのチェックリスト
![]() 坂尾陽弁護士
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
Contents
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
M&A契約の「紛争解決条項」とは?なぜ最初に固めるべきか
M&A契約では、表明保証や補償、価格調整などの中核条項に目が行きがちです。一方で、実際に紛争になったとき、最初に効いてくるのが「紛争解決条項」です。
紛争解決条項は、乱暴にいえば次の3点を決める条項群です。
- どこで争うか(裁判ならどの裁判所か=専属的合意管轄)
- どの手続で争うか(裁判か、仲裁か、調停・ADRを挟むか)
- どの法で判断するか(準拠法条項)
この3点が曖昧だと、紛争の中身(表明保証違反があったか等)に入る前に、「そもそもどこで争うのか」「裁判できるのか」「どの法で読むのか」で先に揉めます。初動が遅れ、コストも膨らみやすくなります。
なお、M&Aの紛争対応の全体像(訴訟・仲裁・調停の選び方や進め方)を俯瞰したい場合は、M&A紛争の解決手段【訴訟・仲裁・調停】と戦略もあわせて読むと、条項設計の判断がしやすくなります。
M&Aの専属的合意管轄(裁判管轄条項)の押さえどころ
「専属的合意管轄」とは、当事者が合意で、特定の裁判所(例:東京地方裁判所)だけで争うことを決める条項です。M&Aのように契約書が精緻な取引では、裁判を選ぶ場合、ほぼ必ず検討対象になります。
実務で押さえたいポイントは、主に次のとおりです。
- 専属か非専属か:他の裁判所にも提起できる余地を残すのか、一本化するのか
- どの裁判所か:第一審をどこにするか(例:東京地裁/大阪地裁など)
- 対象となる紛争範囲:「本契約に起因・関連する一切の紛争」など、どこまで広げるか
- 当事者の範囲:保証人・親会社・グループ会社が関与する設計か(署名当事者以外に当然に効くわけではない)
- 複数契約との整合:基本契約と付随契約(エスクロー、TSAs等)で管轄がズレていないか
たとえば、M&Aで多い落とし穴が「契約違反の主張だけでなく、不法行為(説明義務違反等)としても争われる」ケースです。条項の文言が狭いと、契約上は専属的合意管轄でも、別の請求構成で争われたときに論点が出ます(最終的には裁判所の判断になります)。
また、クロスボーダー案件では「相手方資産がどこにあるか」「判決をどこで回収するか」まで含めて、裁判地を考える必要があります。国内完結の感覚で決めると、勝っても回収が難しい設計になりかねません。
仲裁条項と裁判管轄条項を“両方入れる”設計は要注意です。条項が矛盾すると、手続の入口で争いが長期化しやすくなります(例:一方は仲裁、もう一方は東京地裁専属)。基本は「メインの紛争解決手段」を一本化し、例外(仮差押え等)をどう扱うかを整理します。
M&Aの仲裁合意(仲裁条項)の押さえどころ
「仲裁合意(仲裁条項)」は、裁判ではなく仲裁で紛争を解決することを当事者が合意する条項です。仲裁のメリットとしてよく挙がるのは、秘密性や、クロスボーダーでの中立性・執行可能性です。一方で、仲裁は設計の自由度が高い分、条項が薄いと揉めます。
最低限、検討したい設計要素は次のとおりです。
- 仲裁機関/仲裁規則:どの機関・規則に従うか(アドホックか機関仲裁か)
- 仲裁地(seat):どの国・都市を仲裁地にするか(手続法や裁判所の関与が変わる)
- 言語:日本語/英語など(実務コストに直結)
- 仲裁人の数・選任方法:1名か3名か、選任プロセスをどうするか
- 暫定措置・保全:緊急時にどうするか(裁判所の保全を併用する設計もあり得る)
仲裁は「紛争解決の場」を中立化できる反面、仲裁人報酬や運営コストが重くなることもあります。金額規模・争点の専門性・秘密保持の重要度を踏まえて、裁判と比較することが大切です。
仲裁条項を入れるなら、「とりあえず入れる」ではなく、上記の最低限を決めて、入口で迷子にならない設計にすることが重要です。手続選択のメリット・デメリットを比較したい場合は、(同一カテゴリ内の)**M&A紛争を訴訟・仲裁・調停のどれで解決すべきか【メリット・デメリット】**を参照すると整理しやすくなります。
準拠法条項と、紛争時に効いてくる周辺条項(完全合意・権利不放棄・譲渡禁止)
準拠法条項は、「この契約をどの国の法で解釈し、効果を判断するか」を決める条項です。特にクロスボーダーM&Aでは、準拠法をどうするかで、契約解釈の常識や、損害賠償・解除の考え方が変わり得ます。
ただし注意したいのは、準拠法条項を入れたからといって、あらゆる問題がその法だけで決まるとは限らない点です。だからこそ、準拠法だけを単独で決めるのではなく、管轄・仲裁とセットで矛盾なく設計することが重要です。
そして、紛争時に“地味に効く”のが、次の周辺条項です。
- 完全合意条項
:契約書が当事者の合意の全てである旨を定める条項。交渉経緯や説明資料が争点化したときに効いてきます。
ただし、完全合意条項があるからといって、常に「説明が問題にならない」「不実告知が免責される」というわけではありません。表明保証や開示の設計と一体で考える必要があります。 - 権利不放棄条項
:違反を見逃した・権利行使しなかったとしても、将来の権利行使を妨げない旨の条項。
実務では有用ですが、運用で長期間黙認した場合など、信義則上の問題が出る余地は残ります。条項を置いた上で、通知・是正の運用を丁寧に行うのが大切です。 - 契約譲渡禁止条項
:契約上の地位(権利義務)や権利の譲渡を制限する条項。
M&Aでは、買い手側の組織再編やファンドの投資スキーム、売り手側の再編などで「グループ内移転」ニーズが出ます。全面禁止にすると将来の動きが止まり、例外を広げすぎると相手方保護が薄くなります。誰の同意が必要か、グループ内はどうするか等、設計が重要です。
これらの一般条項をまとめて確認したい場合は、**M&A契約の一般条項(完全合意条項・権利不放棄条項・契約譲渡禁止条項)**もあわせて読むと、紛争解決条項とのつながりが整理しやすくなります。
実務のチェックリスト:複数契約・クロスボーダーで「矛盾」を潰す
M&Aでは、最終契約だけでなく、関連契約・付随合意が複数並びます。紛争解決条項は、ここで矛盾が起きやすい典型ポイントです。
たとえば、次のようなパターンは要注意です。
- 基本契約は「東京地裁の専属的合意管轄」なのに、付随契約に「仲裁合意」が混ざっている
- 準拠法は日本法なのに、仲裁地だけ海外で、言語・規則が未設定
- 「協議→調停→裁判」の段階条項があるが、協議期間やトリガーが曖昧で動けない
こうした事故を防ぐには、契約群を横串で見て、少なくとも次をチェックします。
- 紛争解決条項の“主ルート”は裁判か仲裁か(例外は何か)
- 「本契約に関連する紛争」の範囲は各契約で揃っているか
- 署名当事者の範囲(親会社保証・役員・グループ会社)が想定どおりか
- 準拠法/管轄(or仲裁地)/言語が実務運用できるか
- 通知・協議・是正期間など、前提手続が“動く設計”か
![]() 坂尾陽弁護士
坂尾陽弁護士
まとめ
- M&A契約の紛争解決条項は「どこで/どうやって/どの法で」争うかを決める、最重要の一般条項
- 専属的合意管轄は、専属・裁判所・対象範囲・当事者範囲・複数契約との整合がポイント
- 仲裁合意は、機関・仲裁地・言語・仲裁人・保全など“最低限の設計”を決めないと入口で揉める
- 準拠法条項は単独で完結しない。完全合意条項・権利不放棄条項・契約譲渡禁止条項も紛争時に効く
- 複数契約・クロスボーダーでは「矛盾の排除」が最優先。条項の横串チェックが有効
関連記事・次に読むべき記事
- M&A紛争の解決手段【訴訟・仲裁・調停】と戦略
- M&A紛争を訴訟・仲裁・調停のどれで解決すべきか【メリット・デメリット】
- M&A契約の一般条項(完全合意条項・権利不放棄条項・契約譲渡禁止条項)
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします