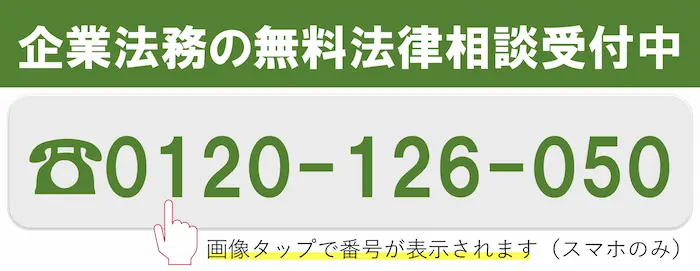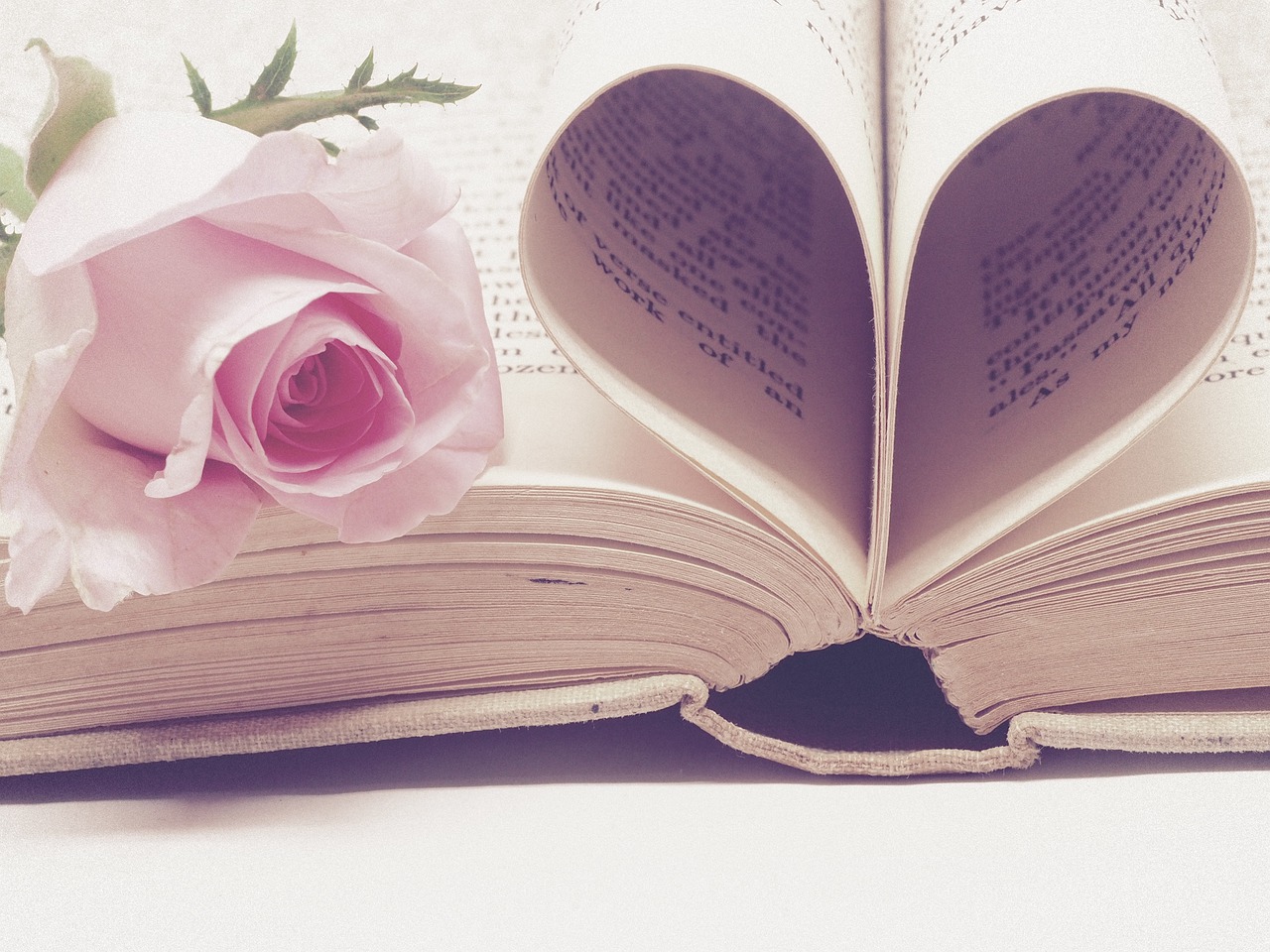会社法139条は、譲渡制限が付された株式の「承認をするか否か」を、どの機関がどのように決定し、譲渡等承認請求をした人に通知するかを定めています。
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会とされますが、定款で別段の定めをすることで柔軟な設計が可能です。ただし、定款自治には限界もあり、承認機関を過度に下位の機関へ委ねることは制約があります。
【一部抜粋:会社法139条(譲渡等の承認の決定等)】
第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
…(以下略)…
※全文はe-Gov法令検索(会社法139条)をご参照ください。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
承認機関の基本ルール
取締役会設置会社 vs. 非設置会社
- 取締役会設置会社:原則として取締役会の決議
- 取締役会非設置会社:原則として株主総会の決議
定款による例外
- 会社法139条1項但書では、定款で別段の定めをすることが認められています。
- 例:譲渡制限種類株式については、その種類株主総会を承認機関とするケース
- 代表取締役・執行役に承認権限を委任する場合は、一定の基準を明確化することが求められる等、裁量が無制限ではない点に注意が必要です。
承認決定と通知義務
承認または不承認を決定した場合、会社は譲渡等承認請求者に対して「決定内容の通知」をしなければなりません(会社法139条2項)。この通知を怠ると、会社法145条の規定によりみなし承認が成立するリスクがあるため、特に取締役会の決議後は素早い通知が欠かせません。
- みなし承認リスク
- 請求日から2週間(定款で短縮可)が経過しても不承認の通知をしない場合、承認したものとみなされる(会社法145条1号)。
- 公開会社で株主総会を承認機関としている場合は、招集手続に時間がかかり、スケジュール的に不承認が困難になるおそれがあります。
特別利害関係人の扱い
取締役会を承認機関とする場合
譲渡当事者が取締役であるときは、株式譲渡決議について特別利害関係取締役(会社法369条2項)に該当し、議決に参加できない可能性があります。譲渡人・譲受人の別を問わず、特別利害関係に当たるとの解釈が有力です。
株主総会を承認機関とする場合
譲渡株主自身は、株主総会決議において特別の利害関係人に該当します(会社法831条1項3号)。この場合、特別利害関係人が議決権を行使していたとしても、それだけでは自動的に決議が無効になるわけではなく、「著しく不当な決議」との評価が必要です。
解散や機関設計の変更と承認機関
- 機関設計の変更
- 取締役会設置会社が取締役会を廃止した場合、承認機関は自動的に株主総会に移行します。定款で異なる取り決めがない限り、会社法139条1項本文に戻るイメージです。
- 解散時
- 解散して取締役会が消滅した場合も、特別な規定を設けていなければ株主総会が承認機関となります。
実務で押さえておきたいポイント
- 承認機関の設定
- 非公開会社の場合、定款による柔軟な設計が可能ですが、代表取締役・執行役を承認機関とする際は注意が必要。
- 通知の徹底
- 2週間以内の不承認通知を怠ると、みなし承認となるリスクがあるため、社内フローを整備しておくことが大切。
- 特別利害関係人の除外
- 公正な決議を行うために、譲渡当事者が決議に直接影響を及ぼさないルールづくりが必要。
- 機関設計変更時の定款整備
- 取締役会を廃止・設置する場合など、タイミングを誤ると承認手続に混乱が生じる可能性があります。
まとめ
会社法139条は、譲渡制限株式を発行する会社にとって非常に重要な条文です。実務担当者は、承認機関の選定と通知手続、そしてみなし承認リスクを十分に理解しておく必要があります。特に非公開会社では定款によって承認機関を変えられるメリットがある一方、裁量権が大きい機関の判断には善管注意義務・忠実義務が伴うことにも留意しましょう。
さらに詳しい株式譲渡手続や、会社法140~143条の買取義務などについては、株式の譲渡を承認しない場合の買取義務(会社法140条~143条)もご参照ください。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)