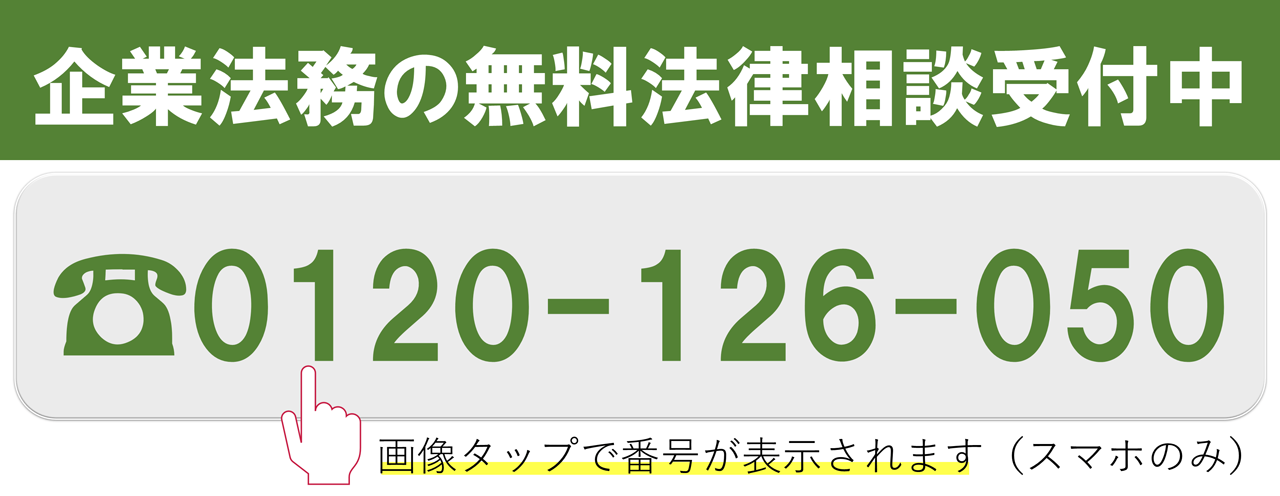上場企業以外の会社においては、ほとんどの場合、発行する全株式の内容として、譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨が定められています(譲渡制限株式:会社法107条1項1号)。株式の譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止し、譲渡人以外の株主の利益を保護することにあります。
株式全てが譲渡制限株式である会社を非公開会社と言いますが、非公開会社においては株式が譲渡される場面は決して多くありません。もっとも、経営陣の対立や事業承継等の場面で譲渡制限株式の譲渡が問題になるケースは相当数あります。
この記事では譲渡制限株式の譲渡承認請求に関する条文を紹介し、問題なるポイントについて解説します。
企業法務・顧問弁護士の無料相談実施中
譲渡承認の請求に関する問題点(会社法136条・137条)
(株主からの承認の請求)
第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
譲渡制限株式の譲渡による取得についての承認を株式会社に請求できるのは、譲渡人である株主と譲受人である株式の取得者です。会社法136条は株主による譲渡承認請求について、会社法137条は株式の取得者による譲渡承認請求についてそれぞれ定めています。
承認を得ない譲渡の効力
株式会社による譲渡承認を得ないまま、譲渡制限株式を譲渡した場合、当事者間における譲渡は有効ではあるものの、会社との関係では譲渡は無効であり会社は譲渡人を株主として扱う義務があるとされています。譲渡制限株式を競落において取得した場合も同様であり、譲渡承認を得ていない以上、会社は譲渡人を株主として扱うべきとされています(最高裁昭和63年3月15日判決)。
会社法137条が株式の取得者からの譲渡承認請求を認めるのは当事者間において譲渡が有効であることを前提としていますし、また、承認の対象は譲渡による株式の「取得」であり当事者間の譲渡自体は承認なく行うことができると考えられるからです。
なお、譲渡制限株式の場合は株主名簿の名義書換請求を行うためには譲渡承認を得ている必要があるので(会社法134条)、承認を得ずに譲渡をしても株主名簿の名義書換えを行うことはできません。
譲渡承認が不要である場合
譲渡制限株式の制度趣旨は、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止し、譲渡人以外の株主の利益を保護することにあります。そのため、株主が一人である会社において当該株主が行った譲渡は会社に対する関係でも有効となりますし(最高裁平成5年3月30日判決)、株式譲渡について全株主の同意を得れば当該譲渡は会社に対する関係でも有効となります(最高裁平成9年3月27日判決)。
取締役会設置会社において譲渡承認は取締役会決議で行うことになりますが(会社法139条1項)、株主の意見と取締役会の意見が相違した場合には、取締役会による譲渡承認決議は欠くにも関わらず株主が株式譲渡をすることがあり得ます。このような場合、取締役会が譲渡を承認しなかったとしても、株主による株式譲渡が優先されることになります。
非公開会社においては主要株主が代表取締役社長であることがほとんどです。しかし、社歴が長い会社や規模が大きい会社では株主と経営陣(取締役会の構成メンバー)が異なる場合があります。例えば、創業者一族である主要株主が経営に疲れたため、会社の経営を他の従業員に任せる場合があります。このようなときに、主要株主と後を任された従業員社長の意見が食い違った場合、従業員社長の意向に関わらず主要株主が株式を第三者に譲渡することがあるので注意が必要ということになります。
譲渡の意義
譲渡制限株式は、当該株式の「譲渡」による取得について株式会社の承認を要するものです。譲渡とは特定承継を言います。相続、合併、会社分割等は一般承継と整理されており、「譲渡」に該当しないため、相続、合併、会社分割等の一般承継による譲渡制限株式の取得には承認は不要と解されています。
その全資産及び負債を承継する相続、合併に比べて、会社分割は承継する資産・負債を選択できる点で実質的には特定承継のようにも思われます。しかし、会社法上は会社分割による承継も一般承継と解されているため、会社分割による譲渡制限株式の取得には承認は不要とされているようです。
もっとも、会社分割と同時に譲渡制限株式を剰余金配当する人的分割を行う場合は譲渡による取得に該当し、承認を要すると解されています。また、事業譲渡は組織再編行為ではありますが一般承継ではなく特定承継と解されているため、事業譲渡による譲渡制限株式の取得については承認が必要なことになります。
会社法においては「譲渡」の意義に関して、一般承継が譲渡に含まれるかは色々な場面で問題となるので注意が必要です。例えば、株式譲渡の対抗要件に関する会社法130条の解釈においては、相続その他の一般承継も譲渡に含むと解されており違いがあります。
(参考)株式譲渡の対抗要件(会社法130条)v
譲渡制限株式の担保設定
譲渡制限株式に質権・譲渡担保権等の担保権を設定することについて承認は不要です(最高裁昭和48年6月15日判決)。もっとも、担保権を設定段階において譲渡承認が不要なだけであり、担保権が実行された場合には当該株式を取得するために譲渡承認が必要となります。
この場合、担保権を実行されて株式を奪われる株主の協力を期待することは難しく、実務的には当該株式を取得する担保権者側が譲渡承認を請求することになると思われます(会社法137条1項)。株主の協力を得られないと、株券発行会社で株券を預かっていない限り、確定判決等を得た上で譲渡承認を請求しなければならず(会社法137条2項、会社法施行規則24条1項1号)、非常に煩雑な手続となるので注意が必要です。
定款におけるみなし承認の定め
譲渡制限株式の譲渡による取得を承認する旨の定めを定款で規定することも可能です(みなし承認:会社法107条2項1号ロ、会社法108条2項4号)。なお、会社法145条により株式会社が承認をしたとみなされる場合もありますが区別が必要です。
譲渡制限株式の趣旨は、株主を人的な信頼関係がある者に限定することが第一義的な趣旨ですが、そうであれば既存株主間の株式譲渡に制限を課す必要はないはずです。しかし、現行の譲渡制限株式については株主間の譲渡も原則として承認を要するとされています。そこで、みなし承認の定めとして、株主間の譲渡に関しては承認を要しない旨を定めることが実務上一般的に行われています。
なお、譲渡する株主の属性による区別(従業員株主以外の譲渡は承認不要)は株主平等の原則に反するため定款の定めが無効と解されています(江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」236頁)。また、一定数未満の株式の取得については会社の承認を不要とする旨の定めについても、登記実務上無効と取り扱われているようです。
株式取得者による譲渡承認請求の手続き
会社法137条1項は、株式取得者による譲渡承認請求ができる旨を定めています。しかし、株式取得者からの譲渡承認請求は、当該株式の株主と共同して行うことが原則とされています(会社法137条2項)。
もっとも、譲渡人である株主が譲渡を望んでいる場合は、譲渡人である株主から譲渡承認請求をすることが実務上は一般的です。そのため、株式取得からの譲渡承認請求は、担保権や強制執行の実行等によって譲渡人=株主が譲渡を望んでいないにも関わらず、株式を取得したケースが多くを占めることになります。
この場合、譲渡人=株主が譲渡を望んでいないことから、譲渡承認請求について当該株式の株主による協力を期待することは困難と思われます。従って、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして定められている会社法施行規則24条を利用して、株式取得者からの譲渡承認請求を行うことになります。
仮装譲渡・権利濫用による譲渡承認請求
原則として、反対株主の株式買取請求権が生じない場面において、株式会社や主要株主に対して株式を買い取らせることはできません。しかし、株式の譲渡を行ったとして、株式会社に対して譲渡承認を請求し、会社が不承認決議をした場合には、会社又は指定買取人が株式を買い取る義務が生じます(会社法140条)。そのため、株式取得者は会社・指定買取人に買い取らせることを目的であるとして、仮装譲渡や権利濫用の主張がなされることがあります。
この点について、譲渡承認の見込みがないことを承知の上で株式の譲渡を受け、かつ、当事者間で譲渡代金の授受が完了していない事案において、裁判所は仮装譲渡・権利濫用であるとの主張を認めませんでした(福岡高裁平成21年5月15日決定)。譲渡承認請求や売買価格決定の申立ては法律に定められた手続きであり、法的手続きに則ってなされた譲渡承認請求や売買価格決定の申立てについて、仮装譲渡や権利濫用であると裁判所が認めるケースは非常に限られたものであると思われます。
譲渡承認請求の方法(会社法138条)
(譲渡等承認請求の方法)
第百三十八条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの株式取得者の氏名又は名称
ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
譲渡承認請求の方法については、会社法138条において譲渡承認請求を行うときに以下の事項を明らかにするべき旨が定められています。
- 譲渡制限株式の種類・数
- 株式取得者の氏名・名称
- 譲渡不承認の場合に会社・指定買取人による譲渡制限株式の買取請求を行うときはその旨
口頭による譲渡承認請求
会社法制定により譲渡承認請求を書面で行う必要はないこととされ、口頭による譲渡承認請求も適法であると考えられます。もっとも、事後的な紛争を予防するために、定款において書面による譲渡承認請求に限定することは可能と解されます。
なお、口頭による譲渡承認請求も適法であり、かつ譲渡承認請求に必要な事項は基本的なものに限られていることから、交渉段階において譲渡承認請求に必要な事項が明らかになると、それが譲渡承認請求に該当し2週間の経過によって会社法145条により譲渡を承認したとみなされるリスクがあるので注意が必要です。
誰に対して譲渡承認請求を行うべきか(名宛人の問題)
譲渡承認請求は「株式会社に対し」行う旨が会社法136条・137条に定められています。実務的には、通常の場合は株式会社の代表取締役宛てとの記載により譲渡承認請求を行うこととなります。しかし、代表取締役が実は適法に選任されていなかった場合、その代表取締役宛ての譲渡承認請求は有効かが問題となり得ます。
この点について、譲渡人である株主にとって代表取締役が適法に選任されているかを知ることは困難なことからすれば、宛先の合理的意思解釈として譲渡承認請求が株式会社に対するものであれば適法であると考えられます。また、意思表示の効力は到達時に生じますが、到達とは代表取締役や受領権限者が受領・了知する必要はなく、了知可能な状態に置かれれば足りると解されています。そうすると、株式会社の代表取締役宛ての譲渡承認請求がなされた場合、その後に当該代表取締役がその地位に無かったと判断されたとしても、本店所在地で従業員が譲渡承認請求を受領すれば株式会社に到達したと判断されることになると考えられます(東京地裁平成30年3月22日判決)。
他の請求と同時になされた譲渡承認請求
株主が譲渡承認請求と他の請求(会社に対する債権の買取請求)を同時に行っており、両者は不可分一体の意思表示であると考えられる場合における譲渡承認請求の効力はどのように考えるべきでしょうか。
この点、譲渡承認請求のみを対象に手続きを進めて良いかを株主に確認をしていると、会社法145条のみなし承認が認められる2週間以内に結論を出す時間的余裕がなくなることも多いと考えられます。そのため、他の請求と同時になされた譲渡承認請求は無効であるとするのが有力な見解です。
企業法務・顧問弁護士の無料相談実施中

- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立