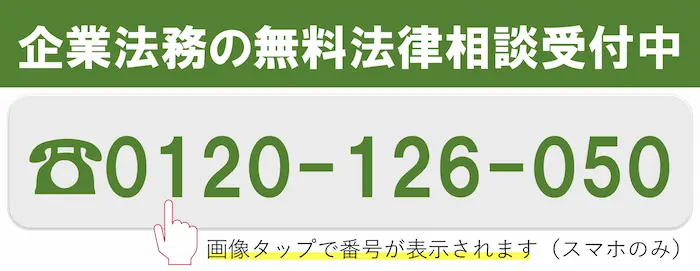(株主の平等)
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
会社法109条1項は、株主が保有する株式の内容・数に応じて平等に取り扱われるべきという株主平等の原則を定めています。他方で、会社法109条2項は公開会社でない株式会社において株主ごとに異なる取り扱う旨の定め(属人的定め)を許容しています。
株主を差別的に取り扱うことが株主平等の原則に反するか否かについて、裁判例は差別化する目的の必要性と手段の相当性を基準に判断しています。実務上採用されている制度が株主平等の原則に反しないかについて制度ごとに解説します。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
株主優待制度の当否
一定数以上の株式を保有する株主に対し、株式数ごとに内容を変えた株主優待制度を採用している会社は少なくありません。株主優待の内容は持株数に厳密に比例したものではない場合、株主平等の原則を定める会社法109条1項に反しないかが問題となります。
この点、一般論としては、株主優待制度が株式数に着目した合理的な内容であれば会社法109条1項に反しないと考えられています。株主優待制度は実務上定着しており、社会的に妥当な制度であると考えられていることも許容される理由かと思われます。
もっとも、裁判例においては基準を超えた株主優待券の交付について、違法な利益供与とされたり又は取締役の責任を追及されたりしたものがあるようです(高知地裁昭和62年9月30日判決、高松高裁平成2年4月11日判決)。例えば、高知地裁昭和62年9月30日判決は、1000株以上保有する株主は、株式を一人で保有するより500株ずつに分ければより多くの株主優待券を取得できることに着目し、大量に株式を保有する株主が架空の人物に株式譲渡を仮装して基準を超えた株主優待券を取得していた事案でした。裁判所は、株主優待制度自体を否定したものではありませんが、基準を超えた株主優待券の交付について違法な利益供与による責任を認めたものです。
従業員持株制度における奨励金支給
従業員持株制度が採用されている場合、従業員が株式を取得しやすくできるように奨励金を支給することが少なくありません。株主である又は株主となる者に対してこのような奨励金を支給することは株主平等の原則に反するように思われます。
この点について、裁判例では奨励金の支給は株主の地位に基づくものではなく、従業員の地位に基づき行われるものであるから株主平等の原則に反しないと判断されています(福井地裁昭和60年3月29日判決)。このように判断する場合、従業員の地位に基づく支給であるというために、従業員の給与水準等に照らして奨励金の支給が過大なものではない等のように従業員の福利厚生として適正な水準でなされていることがポイントになるでしょう。
また、従業員株主については、株主総会を円滑に運営したい会社が株主総会において従業員株主を優先的に取り扱うことが問題になることがあります。例えば、最高裁平成8年11月12日判決は、電力会社において原発反対派株主による議事進行の妨害のおそれがあったため、従業員株主を株主総会において事前に入場させ、前方に着席させたことが不適切なものであったと判断しています。もっとも、最高裁は、株主は希望する席に座れなかったものの、株主としての権利行使を妨げられたものではなく法的利益が侵害されたということはできないとして、会社の不法行為に基づく損害賠償責任を否定しています。
買収防衛策における株主の差別的取扱い
買収防衛策の導入が株主平等の原則に違反しないか問題になった有名な事例として、ブルドックソース事件があります。ブルドックソース事件においては、差別的な行使条件・取得条件が付された新株予約権の無償割当てが株主平等の原則に反するかが問題となりましたが、最高裁は、会社の企業価値が毀損され株主の共同の利益が害されるような場合において、株主を差別的に取り扱ったとしても、その取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、株主平等の原則に違反しないと判断しています(最高裁平成19年8月7日判決)。
この最高裁判決は、株主平等の原則に違反するか否かは、株主の共同の利益が害されるという差別的取扱いの必要性とその手段の相当性という2つの判断基準により決定されることを示したものと考えられています。また、株主の共同の利益が害されるかは、株主自身により判断されるべきであり、株主総会の判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵がない限り、株主総会の判断が尊重されるべきとしています。
なお、東京高裁平成20年5月12日判決は、差別的な取扱いを内容とする新株予約権無償割当てを株主平等の原則に反するとしました。この事案について、裁判所はブルドックソース事件判決の枠組みに沿って判断し、この事案においては現経営陣の経営権を維持するために取締役会決議に基づいて新株予約権の無償割当てがなされていることから株主平等の原則の例外として許容される場合に該当しないとしたものです。
スクイーズアウト(少数株主の締出し)
スクイーズアウトとは、大株主が少数株主の株式を強制的に取得することにより、少数株主を会社から締め出すことをいいます。例えば、中小企業のM&Aにおいてオーナー株主から株式を譲渡した後に小口の株主を締め出すことで会社運営の円滑化を図ったり、公開買付け後にスクイーズアウトを実施することで完全子会社としたりするケースがあります。
スクイーズアウトは、形式的には株主を持株数に応じて扱っているものの、実質的には一定数以上の株式を保有しない少数株主を狙い撃ちにして追い出すものであるため、株主平等の原則の趣旨に反するようにも思われます。
平成26年会社法改正前はスクイーズアウトの手法として、株式併合や全部取得条項付種類株式が用いられることがありましたが、裁判所は株式併合や全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズアウトは株主平等の原則に違反しないと考えているようです(株式併合について東京地裁平成26年2月10日判決・平成26年12月15日判決、全部取得条項付種類株式について東京地裁平成22年9月6日判決参照)。裁判所は、少数株主が締め出されるのはすべての株主に同じ条件が適用され、会社法に従って処理をした結果にすぎないことから株主平等の原則に反するものではないと考えていると思われます。
もっとも、平成26年会社法改正により、少数株主を保護するための会社法171条の3、182条の3、184条の3等の規定が整備されました。今後はスクイーズアウトの問題はこれらの規定の解釈を巡って判断されることになるでしょう。
属人的定め(会社法109条2項)
属人的定めとは、公開会社でない株式会社において、会社法105条1項各号に掲げる権利について株主ごとに異なる取扱いをする定款の規定です。公開会社ではない株式会社においては、株主同士の関係が緊密であるため株主に着目した取扱いをするニーズがあると考えられたことから、株主平等の原則にもかかわらず属人的定めが許容されています。
例えば、株式数ではなく頭数によって議決権や剰余金配当を認めたり、特定株主にだけ特別の剰余金配当請求権を認めたり等の定めが考えられます。
属人的定めを事後的に設けるためには、株主総会の特殊決議が必要となります(会社法309条4項)。また、異なる取扱いを受ける株主の株式は種類株式とみなされ会社法の適用を受けますが(会社法109条3項)、商業登記上は種類株式とは扱われないので登記はされません。
どのような属人的定めが許容されるかについて、裁判所は属人的定めにおいても株主平等の原則と同様に目的の正当性・合理性と手段の相当性という観点から判断しているようです。例えば、東京地裁立川支部平成25年9月25日判決は、特定の株主を経営から実質的に排除し、現経営陣の会社支配を盤石にするために属人的定めを置く定款変更をする旨の決議は目的の正当性を欠いており株主平等の原則の趣旨に違反すると判断しています。さらに、株主の監督是正権を行使できなくなり、株主としての財産権を大幅に制約されたにもかかわらず、経済的代償措置がないことから手段の相当性も欠いているとしています。
なお、東京地裁平成27年9月7日判決は、定款変更によらずにした属人的定めに当たる株主全員の合意を有効と認めました。この事案において、裁判所は属人的な定めについて全株主が同意しているため権利を害される株主がいないことから会社法109条2項の趣旨に反することはなく、定款変更の形式が取られなかったことのみを理由に属人的定めの効力が否定されることは禁反言の見地から相当ではないと判示しています。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします