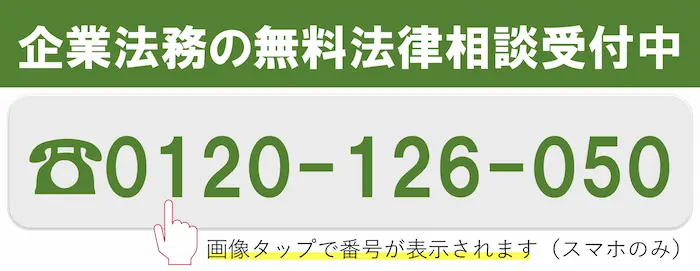譲渡制限株式の譲渡が承認されず、株式会社又は指定買取人が当該株式を買い取る場合の売買価格の決定方法について定めているのが会社法144条です。譲渡制限株式の売買価格は、当事者間の協議又は裁判所に対する売買価格決定の申立てを行うことで決定され、いずれもない場合には1株当たり純資産額に株式数を乗じた金額とされます。
この記事では会社法144条の条文を紹介し、譲渡制限株式の売買価格の決定について、手続きや算定方法の考え方等について解説します。
(売買価格の決定)
第百四十四条 第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
5 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
6 第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
7 前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
売買価格の決定手続き
当事者間の協議による売買価格の決定
譲渡制限株式の譲渡が承認されなかった場合、まずは株式会社・指定買取人と譲渡等承認請求者間の協議により売買価格を決定することが考えられます(会社法144条1項・7項)。しかし、実務上は、株式会社等と予め株式の買取交渉を行っており、その中で価格等が折り合わないため、第三者に対する株式の譲渡承認請求がなされるという流れも少なくありません。つまり、事前に価格交渉が決裂しているため、改めて当事者間の協議によって売買価格の合意が成立する見込みがないことも多いです。
譲渡制限株式の売買価格についての事前の合意
もっとも、売買価格について当事者間で事前に合意がなされるケースもあります。例えば、株主間契約において先買権を付して価格の合意が存在する場合や、従業員持株会において退会時の売買価格について合意が存在する場合等が考えられます。
そして、株式の売買価格に関する事前の合意は、特段の事情がない限り、有効であると考えられています(最高裁平成21年2月17日判決)。例えば、東京地裁平成27年11月12日決定は、従業員持株会の解散に伴う保有株式の譲渡について、予め売買価格についての合意がある場合は、株主の投下資本の回収を著しく制限する不合理なものである等の特段の事情がない限り、裁判所は当該合意による価格を売買価格と決定するのが相当であると判示しています。
なお、株式譲渡義務を定める条項の有効性に関しては下記記事も参考にしてください。
(参考)株式譲渡に関する会社法上の諸問題(会社法127条~129条)
裁判所に対する売買価格決定の申立ての手続き
会社法141条1項又は142条1項による株式の買取通知の到達日から20日以内であれば、株式会社・指定買取人又は譲渡等承認請求者は、裁判所に対する売買価格決定の申立てを行うことができます。会社法においては、協議が調わないことが申立ての要件とされていないため、協議をせずに売買価格決定の申立てをすることも可能です。
実務上は当事者間の協議による売買価格の合意が成立する見込みがないことも少なくありません。この場合、当事者間の協議と裁判所による売買価格決定の申立てのいずれもない場合には、1株当たり純資産額に株式数を乗じた金額が売買価格となるため、1株当たり純資産額をベースとした価格算定が高すぎると判断すれば株式会社・指定買取人側から、低すぎると判断すれば譲渡等承認請求者側から売買価格決定の申立てを行った方が良いことになります。
なお、売買価格決定の申立てを行ったものの、その途中で裁判上の和解により売買価格を決定することも可能です(非常事件手続法65条)。
1株当たり純資産額を基準とした売買価格の決定と供託金還付請求の手続き
当事者間の協議が成立せず、かつ売買価格決定の申立てがなされなかった場合、1株当たり純資産額に株式数を乗じた金額が売買価格とされます(会社法144条4項・7項)。この場合、株式会社・指定買取人による買取通知をする段階で当該金額が供託されているため(会社法141条2項・142条2項)、譲渡等承認請求者は供託金還付請求を行うことにより売買代金を取得することができます。
供託金還付請求のためには、申立期間内に売買価格決定の申立てがない旨の管轄裁判所の証明書に加えて、当事者の合意が成立していない旨の供託者作成の証明書・印鑑証明書が必要となります。つまり、供託金還付請求を行う譲渡等承認請求者は、供託を行った株式会社・指定買取人から証明書・印鑑証明書を貰う必要があります。もし、株式会社・指定買取人側が任意に協力をしてくれない場合には、供託金還付請求権確認の訴えを行う必要があるので注意が必要です(東京高裁平成20年4月10日判決参照)。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
裁判所による売買価格決定についての論点
売買価格決定に関する裁判所の裁量
譲渡制限株式の売買価格決定の申立てにおいて、裁判所は「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない」とされています(会社法144条3項・7項)。そして、譲渡制限株式の売買価格は、客観的・一義的に定まる株価を確認するものではなく、非訟手続において形成されるものであり、会社法は売買価格の決定を裁判所の合理的裁量に委ねていると考えられます(大阪高裁平成元年3月28日決定、反対株主の株式買取請求に関する最高裁昭和48年3月1日決定・最高裁平成23年4月19日決定も参照)。したがって、裁判所は株価形成に関する諸々の事情を考慮し合理的な裁量の範囲内であれば幅広い算定方法を採用することが認められています。そのため、裁判例において売買価格決定についての考え方は多岐に分かれており、裁判所がどのように売買価格を決定するかを予測することが困難な原因の一つとなっています。
会社法が例示する純資産方式を必ずしも採用する必要はない
なお、会社法144条3項・7項は、裁判所が考慮するべき事情として「株式会社の資産状態」を明示しています。しかし、資産状態は考慮要素の例示にすぎず、裁判所は必ずしも資産状態による株価算定方法である純資産方式を重視又は考慮する必要はないと考えられています。例えば、東京高裁平成20年4月4日決定においては、ベンチャー企業として成長力が大きく、純資産方式を採用すること株式価値を過小に評価するおそれがあるとして、純資産方式を考慮せず収益還元方式のみで売買価格が決定されています。
自己株式取得の財源規制を超過する売買価格の決定
なお、裁判所は売買価格の決定について裁量が認められますが、株式会社が株式を買い取る場合において自己株式取得の財源規制の枠内に収まるように配慮して売買価格を決定することはできないと考えられています。したがって、裁判所が財源規制を超過する売買価格を決定した場合、株式会社は株式を取得できず債務不履行により譲渡等承認請求者から売買契約を解除され、会社法145条3号・会社法施行規則26条3号により譲渡等承認請求が承認されたものとみなされます。
取引相場のない株式について価格算定の考え方
上場会社の株式には取引市場があるため、原則として市場価格を基準として、どの時点や期間の市場価格を採用するか、シナジーやプレミアム等をどのように反映するか等が問題となります。これに対し、非上場会社の株式には取引市場がないため、様々な算定方法を考慮してどのように企業価値・株式価値を算定するべきかを考えることになります。
そこで、どのようなアプローチによる算定方法があるかを紹介し、裁判所が譲渡制限株式の売買価格決定の申立てにおいてどのように算定方法を考慮しているかを解説します。
株価算定における3つのアプローチ
非上場会社の株式の評価方法には以下の3つのアプローチが考えられます。
- インカム・アプローチ
- ネットアセット・アプローチ
- マーケット・アプローチ
評価方法のアプローチごとにどのような算定方式があるかを解説します。
インカム・アプローチは会社や事業から生じる収入やキャッシュフローに着目するものです。主な株価算定方式としては、DCF法・収益還元方式と配当還元方式があります。DCF法・収益還元方式は会社や事業から生じるキャッシュフローや収益に着目した算定方式であり、配当還元方式は株主が企業からどれだけの配当収入を得られるかに着目した算定方式です。
ネットアセット・アプローチは会社の貸借対照表の純資産に着目するもので、主な株価算定方式としては純資産方式が該当します。
マーケット・アプローチは、上場している同業他社の株価や当該株式の取引事例における株価に着目した算定方式です。主な株価算定方式としては類似業種比準方式や取引事例法があります。しかし、類似業種比準方式は課税技術上の観点から考案されたものであり会社法の考えとは合致していません。また、非上場会社の株式には取引事例法がない場合がほとんどです。そのため、類似業種比準方式や取引事例法は過去の裁判例では用いられることがありましたが、近年の裁判例ではほとんど用いられていません。
近年の裁判例においては、DCF法・収益還元法、配当還元方式、純資産方式が主に用いられているため、それぞれの算定方式がどのような場合に用いられるのか、どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説します。
DCF法
DCF法は、将来のフリー・キャッシュ・フローを加重平均資本コストで割り引いて計算し、その後、余剰資金等の非事業用資産を加算し、有利子負債を減算する評価方法です。継続企業における企業価値・株式価値の本源的な評価方法です。
DCF法は株価の算定方式として理論的に最も妥当だと考えられますが、将来に予想されるキャッシュフローの前提となる事業計画が必要であることや、事業計画や資本コストの相当性に不確定な部分があることから、正確かつ客観的な算定が難しい方式だといえます。
裁判例においては、支配株主にとっての株式価値はDCF法による算定が妥当であるとされる傾向にあり、事業計画が存在し、鑑定が活用されるようなときに用いられることが増えています。
収益還元法
収益還元法は、将来の予想純利益を一定の割引率で割り引くことにより株式価値を算定する評価方法です。
将来のキャッシュフローではなく将来の予想純利益に着目するものですが、将来の予想純利益については損益計算書における過去の純利益の推移から比較的容易に見積もることができます。そのため、収益還元法はDCF法の簡便法として位置付けられ、事業計画がなかったり又は事業計画の信憑性が乏しかったりする場合に利用されている手法です。
裁判例においては、支配株主にとっての株式価値を算定する場面において、DCF法が使える事例にはDCF法を、DCF法が使えない事例には収益還元法を利用する傾向があります。
配当還元方式
株主にとって株式を保有することによる直接的な収入である配当金の期待値を資本還元率で割り引くことによる評価方法です。配当還元方式には、配当実績に基づき算定する方法や、内部留保の寄与による将来配当の増加を見込んであるべき配当を用いるゴードン・モデル方式などがあります。
非上場会社の少数株主にとって株式を保有することによるメリットは配当収入を得るだけであることが多いため、裁判例においては少数株主にとっての株式価値は配当還元方式による算定が妥当とされる傾向があります。
しかし、非上場会社においては配当がほとんど行われず内部留保に回されていたり、支配株主は自身や親族を会社の役員にして配当ではなく役員報酬により会社の収益を回収していたりすることが少なくありません。そのため、とくに過去の配当実績に基づいて配当還元方式を適用した場合、株価が不当に低く評価されるという問題があります。
そこで、裁判例においては、役員報酬を配当金の変形とみなして配当還元方式を適用したり(千葉地裁平成3年9月26日決定)、同業種である上場会社の業界平均値を参考に予想配当性向を用いて配当還元方式を適用したり(大阪地裁平成27年7月16日決定)する工夫が見られるところです。
純資産方式
純資産方式は会社の純資産を基準とする評価方法です。会計上の純資産額に基づいて1株当たりの純資産の額を計算する簿価純資産方式、貸借対照表の資産負債を時価で評価し直して純資産額を算出し、1株当たりの時価純資産額を計算する時価純資産方式、個別資産の再調達時価を用いて1株当たり純資産の額を算出する再調達時価純資産方式等があります。
純資産方式は比較的算定が簡単であり、客観性も担保しやすいメリットがありますが、理論的に継続企業の企業価値・株式価値を示すものではないという指摘があります。
もっとも、裁判例においては、株式は会社の資産を化体したものと見ることができる、又は株主は会社が清算段階に至った場合には残余財産の分配を受ける権利があることを踏まえて、純資産方式を採用することも少なくありません。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
譲渡制限株式の株価算定における問題点
裁判所はどのように株価算定方法を考慮しているか
近年の裁判例においては、DCF法・収益還元法、配当還元方式、純資産方式のそれぞれによる株価を算定し、それぞれの方式による株価を一定割合で折衷した金額を採用することが増えています。つまり、譲渡制限株式の売買価格を決定するにあたって、裁判所は、譲受人である会社・指定買取人にとって妥当な株価算定方式と、譲渡人である譲渡等承認請求者にとって妥当な株価算定方式を決定し、その両者を一定割合で組み合わせて最終的な売買価格を決定する傾向があります。
例えば、収益還元法では1000円、配当還元方式では200円、純資産方式では800円と算定する旨の鑑定がなされ、裁判所が収益還元法:配当還元方式:純資産方式を50%:25%:25%の割合で折衷して株価を算定する場合は、500円+50円+200円=750円が売買価格と決定されるイメージです。
札幌高裁平成17年4月26日決定は、支配株主である指定買取人の立場からは収益還元法が妥当であり、少数株主である譲渡等承認請求者からは配当還元方式と純資産方式の中間値が妥当であるとした上で、両者のいずれの立場を重視するのが相当といえる事情がないことから、収益還元方式:配当還元方式:純資産方式=0.5:0.25:0.25の割合で組み合わせる併用方式により売買価格を決定するべきと判断しています。
株式会社・指定買取人と譲渡等承認請求者における株式価値の考慮
裁判所が譲渡制限株式の売買価格を決定するときに重視しているのが、株式会社・指定買取人と譲渡等承認請求者の両方の立場から株式価値を考慮することです。
具体的には、譲受人である会社・指定買取人は一般的に会社・事業を支配しているため、株価算定に当たってはDCF法・収益勧化還元や純資産方式を用いるべきとされます。
これに対し、譲渡等承認請求者は、保有株式数・株式割合や従前の会社における立場を考慮して、少数株主に過ぎないのか、又は譲渡等承認請求者の株式が移転することに伴って経営権の異動が生じると見ることができるかが区別されます。少数株主に過ぎないと判断されれば主に配当還元方式が用いられ、経営権の異動が生じる場合だと判断されればDCF法・収益還元方式や純資産方式を用いるべきとされます。
純資産方式の最低限の株価を画する役割
とくに純資産方式のうち処分時時価純資産方式は、会社が解散した場合における株主が株式から取得できる金額(解散価値)を意味します。したがって、処分時時価純資産方式による株価がDCF法や配当還元方式による株価よりも高い場合、そのような会社は即時に解散して解散価値を株主に分配するべきであり、解散価値が株価の最低限を画するという考えがあります。
例えば、大阪高裁平成元年3月28日決定は、最終的に配当還元法(ゴードン・モデル方式)により売買価格を決定しましたが、解散価値に基づき算出される株式価値は株価の最低限を画する意義を有すると判示しており、配当還元法(ゴードン・モデル方式)により決定された売買価格が純資産方式により算出された株価を上回ることを確認しています。
裁判例においては、理論的根拠は必ずしも明らかではないものの、配当還元方式により算出された株価が不当に低いものであるような場合には、裁判所は純資産方式による株価を加味して妥当な範囲内に株価を調整しているのではないかとも思われます。例えば、東京高裁平成2年6月15日決定は、譲渡等承認請求者はわずか0.16%の株式を保有するにすぎず、少数株主の立場からは配当還元方式が最も合理的であるとしつつも、株式が会社の資産を化体したものであるとして時価純資産方式を加味するべきとし、配当還元方式:純資産方式=7:3の割合で折衷した併用方式を採用しましたが、純資産方式を考慮する割合が30%である理論的根拠等については必ずしも明らかではないように思われます。
純資産方式における清算費用の控除
純資産方式を株価算定に用いる場合において、清算時の公租公課等の清算費用を控除するべきかが問題となります。純資産方式について、株主は会社が清算段階に至った場合には残余財産の分配を受ける権利があることを踏まえて考慮するとの裁判例もありますが、もし残余財産の分配を受けることになった場合には純資産の処分に伴う公租公課や費用等が控除されるため、清算費用に相当する金額は株主が取得できません。そうすると、とくに処分時価純資産方式を用いるような場合には清算費用を控除するべきであると考えられます。
例えば、東京高裁平成2年6月15日決定は、株価算定にあたって時価純資産方式を加味するべきではあるものの、資産の評価差額については法人税等を控除するべきと判示し、純資産方式の算定時に公租公課等の清算費用を控除する立場を明らかにしています。
マイノリティディスカウントや非流動性ディスカウント
少数株主であることを理由に株価を低く算定することをマイノリティディスカウント、非上場会社の株式であり流通性がないことを理由に株価を低く算定することを非流動性ディスカウントといいます。
譲渡制限株式の売買価格を決定する場合において、実質的にマイノリティディスカウントや非流動性ディスカウントが行われることは少なくありません。この点に関して、株式の評価方法により算定される1株当たりの企業価値と第三者に売却したときに得られる交換価値を区別した上で、譲渡不承認の場面における譲渡制限株式の売買価格の決定においては、自らの意思で株式を譲渡しているため交換価値で足りるとする考え方があります。他方で、反対株主の株式買取請求権における公正な価格を決定する場面では、強制的に株式をはく奪される株主を救済するために企業価値を保障すべきと考えられます。
裁判例においては、譲渡等承認請求者の立場が少数株主であると判断された場合、株価が低く評価される傾向にある配当還元方式による算定割合が高くなりますが、これは実質的にマイノリティディスカウントが行われていると考えることができます。また、裁判例においては、15~30%程度の非流動性ディスカウントを明示的に行っているものもあります(大阪地裁平成25年1月31日決定、東京地裁平成26年9月26日決定等)。
非上場株式の売買価格決定に関する裁判例の紹介
非上場株式の売買価格決定に関する裁判例をいくつか紹介し、具体的に裁判所がどのような点を重視しているかを解説します。
大阪高裁平成元年3月28日決定:配当還元方式を採用
大阪高裁平成元年3月28日決定は、ゴードン・モデル方式による配当還元方式を用いて売買価格を決定しています。その理由として、会社を支配していない少数株主・一般株主にとって将来の利益配当に対する期待のみが投資対象であるからとしています。
その上で、配当金が多数者の配当政策に偏って決定されるときは、配当還元法による株価が会社資産の解体価値に満たないこともあり得るので、会社資産の解体価値に基づき算出される株式価格は株価の最低限を画する意義を有するとし、配当還元方式による株価が再調達時価純資産方式による株価を上回っていることを確認し、最終的に配当還元方式のみにより売買価格を決定しました。
東京高裁平成元年5月23日決定:配当還元法:収益還元法:純資産法=6:2:2
東京高裁平成元年5月23日決定は、譲渡等承認請求に係る株式割合は9%に過ぎず譲受人は配当金の取得を主たる利益・目的とせざるを得ないから、基本的には配当還元法を採用するのが相当としています。しかし、継続企業である以上は会社の資産、収益の内容や程度を勘案せざるを得ず、過去の配当額に多くを依拠する配当還元方式のみによることは不十分であり、収益還元法及び純資産法も併用するのが相当だとしています。
その上で、対象株式数は少数株主権の行使を可能とするものであることや、株式会社の代表取締役が将来当該株式を取得する可能性が少なくないことが推認されると指摘し、最終的に配当還元法:収益還元法:純資産法=6:2:2とする算定方式により売買価格を決定しました。
この事案では長年にわたり配当性向15~30%もの配当実績がありました。しかし、配当還元方式による場合は1株924円、収益還元方式による場合は1株2,818円、純資産方式による場合は1株8,284円と大きな開きがあったことから、収益還元方式・純資産方式も各2割程度(合計4割程度)は考慮するべきと判断したのではないかと思われます。
東京高裁平成20年4月4日決定:収益還元方式を採用
東京高裁平成20年4月4日決定は、ベンチャー企業の株価算定において参考になる裁判例です。
裁判所は、譲渡承認に係る株式数は発行済株式総数の40%に当たることから、経営権の移動に準じて取り扱い純資産方式、収益還元方式を検討するべきとしています。なお、この事案では、取引事例も2件程度あったようですが、取引事例は2年前であり件数も少ないとして取引事例法を裁判所は採用しませんでした。
その上で、会社は創業してさほど年月が経過しておらず、資産に含み益がある不動産等は存在しないこと、ベンチャー企業として成長力が大きく、売上は順調に推移しており、今後も同程度の利益が確実に見込まれると指摘し、このような場合に純資産法を採用すると株式価値を過小に評価するおそれがあるため、収益還元法によって評価するのが相当であるとし、収益還元方式のみにより売買価格を決定しました。
大阪地裁平成25年1月31日決定:配当還元法:収益還元法=20%:80%
大阪地裁平成25年1月31日決定は、非流動性ディスカウントやマイノリティディスカウントに明示的に言及している点で注目される裁判例です。
裁判所は、まず継続企業は財産を活用して収益を上げることが予定されているため、収益力が反映されていない純資産方式を採用する必要はないとしました。その上で、少数株主にとって妥当する配当還元方式をある程度考慮するとともに、収益還元方式は資産の価値と収益力をバランスよく配慮した評価方法であり収益還元方式の採用には合理性があるとしています。そして、この事案においては譲渡承認に係る株式は発行済株式総数の約18.9%であったものの、他株主の保有割合も20%前後と同程度であったことから、株式会社の支配を望む他株主にとって無視できないことから、対象株式数自体は議決権の過半数に達していなくても収益還元方式に80%のウェイトを置くことは不合理ではないとしています。
また、非流動性ディスカウントについて、譲渡制限株式は投下資本回収に制約があることを理由に30%程度価格の評価が下がるのが一般的であるとしつつ、本件においては他株主と利害関係が一致すれば配当額を増加させることも可能であるとし、非流動性ディスカウント率を一般的な30%よりも低い15%としたことは合理性を欠くものではないとしています。
また、マイノリティディスカウントについては、譲渡等承認請求者が少数株主であることを考慮し、少数株主にとって妥当な配当還元方式を20%の割合で考慮しるため、それに重ねてさらに少数株主であることを理由にマイノリティディスカウントを行うべきではないと判断しています。。
大阪地裁平成27年7月16日決定:配当還元方式と純資産方式
大阪地裁平成27年7月16日決定は、直接物品の製造・販売事業を行っている事業会社と、その株式を保有するだけで事業活動を全くしていないホールディングカンパニー(純粋持株会社)の2社についての株価算定が問題となった事案です。
まず事業会社については、株式会社が今後も事業活動を継続していくことが予想されること、譲渡承認に係る株式は非支配株主のものであり、譲渡人・譲受人のいずれもが配当の取得を主な利益・目的とせざるを得ない地位にあり、株式売買が実質的には将来の配当に対する期待を売買するのと同視できることを総合すると、対象会社の株式評価について配当還元法を採用するのが最も合理的かつ相当であるとしています。もっとも、実際の配当性向は4~5%と相対的に低水準であったことから、過去の配当実績ではなく、予想配当性向に基づいて配当還元方式を適用しています。この予想配当性向を決定するにあたって、裁判所は業界平均として同業種である非鉄金属・金属製品工業の上場会社の配当性向及び上場会社平均としてく東証1部上場会社の配当性向を考慮している点が注目されます。
他方で、ホールディングカンパニー(純粋持株会社)について、裁判所は、事業活動を全く行っておらず、実質的には事業会社の株式保有のみを目的とするいわゆる資産管理会社であり、その総資産の大部分は事業会社の株式であるとし、ホールディングカンパニー(純粋持株会社)の株価は、子会社である事業会社の株式の時価を基準とした時価純資産法によって評価することが相当であると判示しています。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)