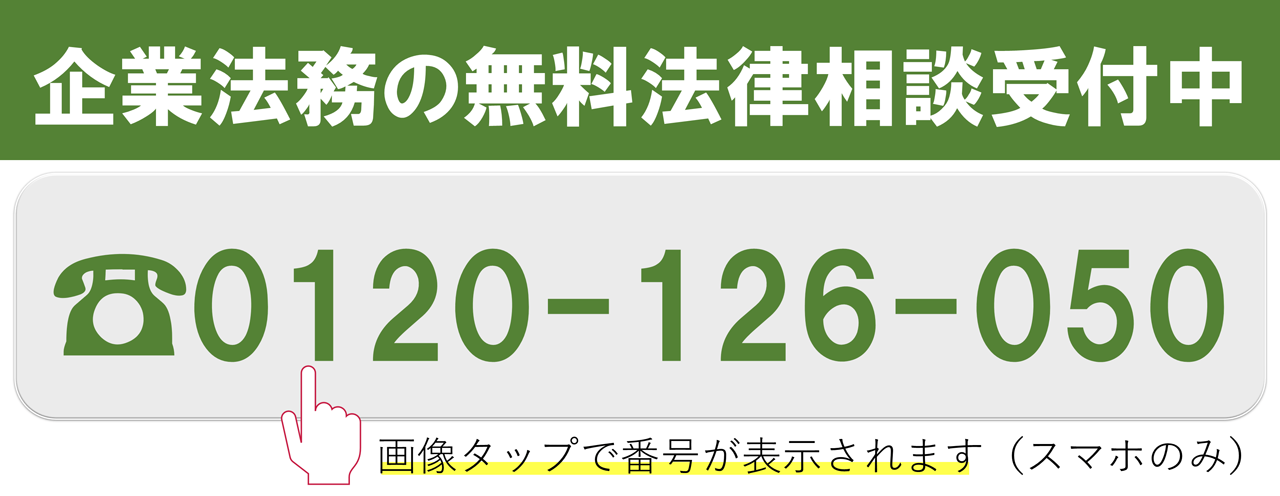(共有者による権利の行使)
第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法106条は株式が共有に属するときの取扱いを定めています。実務的には、中小企業のオーナー株主が死亡し、オーナーが保有していた支配株主が共同相続された場合において、相続人同士で中小企業の支配権を巡る争いの中で問題になることが多い条文です。
企業法務・顧問弁護士の無料相談実施中
権利行使者の選定手続き
会社法106条は、共有に属する株式の権利を行使するためには権利行使者を定め、株式会社にその氏名・名称を通知すべきことを定めるだけであり、具体的にどのように権利行使者を定めるかについて規定していません。
権利行使者を定めることは民法252条の共有物の管理行為に該当するため、各共有者の持分の価格の過半数で権利行使者を定めることができると考えられます(有限会社の事例における最高裁平成9年1月28日判決参照)。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
権利行使者を選定する上では、全共有者に参加の機会を与える必要があると考えられています(大阪地裁平成9年4月30日判決参照)。もっとも、参加の機会を与えても選定の結果が異なるとは考えにくい場合には、共有者の一部が参加しないままの選定も有効となることがあります(東京高裁平成13年9月3日判決、東京地裁平成17年11月11日判決)。
なお、共有者に未成年者とその親権者がいる場合、親権者が未成年者を代理して自分自身を権利行使者に選定しても民法826条の利益相反には該当しないとされています(最高裁昭和52年11月8日判決)。
共同相続による共有株式の権利行使者に関する紛争
中小企業の支配株式が共同相続された場合、法定相続分次第では共有者の持分の過半数で決められた権利行使者が株式全部について恣意的な議決権を行使することで支配権が覆ることがあります。このような場合、権利行使者による共有株式に関する権利行使が権利濫用に該当することがあります。
例えば、大阪高裁平成20年11月28日判決の事案は、同族会社において元々は少数派だったにもかかわらず、法定相続分の過半数を有したため被相続人が保有しており共同相続した株式の権利行使者となり、少数派から人員を取締役に選任した事案でした。裁判所は、わずかの差で議決権の過半数を占めることを奇貨とし、権利行使者の指定について真摯に協議する意思を持つことなく選定した権利行使者の選定・議決権行使は権利濫用にあたると判断しています。
権利行使者の権限
共有株式の権利行使者は、他共有者の意思にかかわらず自己の判断で議決権を行使することができます(最高裁昭和53年4月14日判決)。
また、遺言執行者がいるような場合でも、共同相続された株式について会社に権利行使できるのは遺言執行者ではなく権利行使者であると考えられます。東京地裁昭和57年1月26日判決は、遺言執行者が計算書類・株主帳簿の閲覧を請求した事案において、遺言執行者による権利行使は遺言書通りに株式を帰属させるという遺言内容の執行として必要なものとは言えないとして、遺言執行者による権利行使を否定しています。
権利行使者の選定・通知がない場合の対応
会社法106条に基づく権利行使者の選定・通知がない場合、株式会社が共有株式に関して通知・催告をするときは、会社法126条4項の適用により共有者の一人に対して通知・催告をすれば足りることになります。
また、権利行使者の選定・通知がない場合でも、会社法106条但書により株式行使が権利行使に同意した場合は権利を行使できることになります。このため、発行済株式総数の大部分を共有株式が占めており権利行使者が選定されていないため株主総会の特別決議が成立しないはずにもかかわらず、株式会社が株主総会の特別決議が成立したことを前提に運用されている等の特段の事情があるときは、各共有者は株主としての権利を行使できると考えられます(最高裁平成2年12月4日判決、最高裁平成3年2月19日判決)。このような特段の事情があるときは、株式会社が特別決議の成立という共有株式の権利行使を認めているも同然の自体を生じさせているため、権利行使者の選定・通知がないことを株式会社が主張するのは信義則に反すると考えられます。
会社法106条但書は、あくまで共有株式に係る権利行使が適法な場合において、株式会社の同意による権利行使を認めるものです。共有株式には原則として民法の共有に関する規定が適用されるため、共有株式に係る権利行使が民法の規定に照らして適法でない場合には株式会社の同意があってもそのような権利行使は認められません。最高裁平成27年2月19日判決は、相続人が2名であり各相続人が各2分の1の割合で株式を共同相続した事案において、相続人の一人による権利行使を株式会社が認めたとしても、その権利行使は民法252条本文に定める共有者の持分の過半数で決定されたものではないため適法ではないと判断しています。
企業法務・顧問弁護士の無料相談実施中